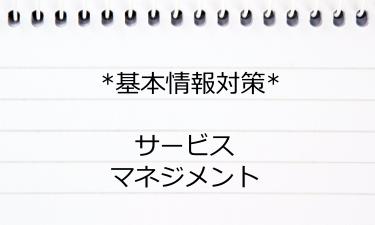
今回の基本情報対策は、サービスマネジメントです。3回目です。システム移行やシステム障害に関する問題のほか、システム監査などの問題を選びました。システム移行は、移行方式によってメリット・デメリットがあるので、整理して覚えておきましょう。
問題 1
システムの移行方式の一つである一斉移行方式の特徴のうち,適切なものはどれか。 (基本情報技術者試験 平成26年春期 午前問55)
(A) 新旧システム間を接続するアプリケーションが必要となる。
(B) 新旧システムを並行させて運用し,ある時点で新システムに移行する。
(C) 新システムへの移行時のトラブルの影響が大きい。
(D) 並行して稼働させるための運用コストが発生する。
正解は C。
一斉移行方式とは、システムの移行において、旧システムを停止してから移行作業を行い、移行後に新システムを稼働させる方式です。
順次移行方式
旧システムを稼働させたまま移行作業実施
長所: トラブル時の影響が小さい
短所: 並行稼働のためコストが大きい
一斉移行方式
旧システムを停止させて移行作業実施
長所: 稼働させないためコストは小さい
短所: トラブル時の影響が大きい
(A) 新旧システム間を接続するアプリケーションが必要となる。
これは誤りです。順次移行方式の説明です。新旧両方のシステムを稼働させます。
(B) 新旧システムを並行させて運用し,ある時点で新システムに移行する。
これは誤りです。順次移行方式の説明です。安定動作が確認できた時点で旧システムを停止します。
(C) 新システムへの移行時のトラブルの影響が大きい。
これは正しいです。一斉移行方式の説明です。新旧を停止させているため、トラブルが発生すると影響が大きくなります。
(D) 並行して稼働させるための運用コストが発生する。
これは誤りです。順次移行方式の説明です。
問題 2
ITサービスマネジメントにおける"既知の誤り(既知のエラー)"の説明はどれか。 (基本情報技術者試験 平成26年春期 午前問56)
(A) 根本原因が特定されている又は回避策が存在している問題
(B) サービスデスクに問合せがあった新たなインシデント
(C) サービスマネジメント計画での矛盾や漏れ
(D) 静的検査で検出したプログラムの誤り
正解は A。
既知の誤りとは、根本原因が特定されており、暫定的な回避策または、恒久的な対応策が存在する問題です。
(A) 根本原因が特定されている又は回避策が存在している問題
これは正しいです。
(B) サービスデスクに問合せがあった新たなインシデント
これは誤りです。新たなインシデントは、原因が特定されているとは限らないので、既知の誤りではありません。
(C) サービスマネジメント計画での矛盾や漏れ
これは誤りです。サービスマネジメント計画の矛盾や漏れは、既知の誤りではありません。
(D) 静的検査で検出したプログラムの誤り
これは誤りです。静的チェックによる誤りは、既知の誤りではありません。
問題 3
"システム管理基準"に基づいて,システムの信頼性,安全性,効率性を監査する際に,システムが不正な使用から保護されているかどうかという安全性の検証項目として,最も適切なものはどれか。 (基本情報技術者試験 平成26年春期 午前問60)
(A) アクセス管理機能の検証
(B) フェールソフト機能の検証
(C) フォールトトレラント機能の検証
(D) リカバリ機能の検証
正解は A。
システムの安全性では、システムが不正アクセスから保護されているかを検証します。機密性とも呼ばれます。
システムの信頼性
品質は十分であるか。障害を予防でき、発生時に復旧できるか
システムの安全性
不正アクセスから保護されているか
システムの効率性
業務に効果的に活用できるか、費用対効果があるか
(A) アクセス管理機能の検証
これは正しいです。
(B) フェールソフト機能の検証
これは誤りです。フェールソフト機能の検証は信頼性にあたります。
(C) フォールトトレラント機能の検証
これは誤りです。フォールトトレラント機能の検証は信頼性にあたります。
(D) リカバリ機能の検証
これは誤りです。リカバリ機能の検証は信頼性にあたります。
問題 4
システム障害の発生時に,オペレータが障害の発生を確実に認知できるのはどれか。 (基本情報技術者試験 平成26年秋季 午前問58)
(A) サーバルームに室内全体を見渡せるモニタカメラを設置して常時監視する。
(B) システムコンソールへ出力させるアラームなどのメッセージに連動して,信号表示灯を点灯する機能や報知器を鳴動する機能を設ける。
(C) 障害発生時にスナップショットダンプやメモリダンプを採取する機能を設ける。
(D) 毎日定時にファイルをフルバックアップする機能を設ける。
正解は B。
システム障害時には、電子メールの送信や、画面・パネルの点滅、信号表示灯の点灯などにより、担当者に通知する仕組みが必要です。
(A) サーバルームに室内全体を見渡せるモニタカメラを設置して常時監視する。
これは誤りです。モニタカメラでは、人的な行為や災害による障害に気付くことはできますが、システム内部の技術的な障害は検知できません。
(B) システムコンソールへ出力させるアラームなどのメッセージに連動して,信号表示灯を点灯する機能や報知器を鳴動する機能を設ける。
これは正しいです。
(C) 障害発生時にスナップショットダンプやメモリダンプを採取する機能を設ける。
これは誤りです。スナップショットダンプやメモリダンプは障害の調査には役立ちますが、障害の発生を検知することはできません。
(D) 毎日定時にファイルをフルバックアップする機能を設ける。
これは誤りです。バックアップは障害後の復旧に利用します。障害の発生を検知することはできません。